| → 用語集インデックス |
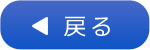 |
| 治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
| プラシーボ効果 |
| Placebo Effect |
| 解説(1) |
| プラシーボ効果とは? |
薬効成分を含まない「プラセボ」(偽薬)を薬だと偽って投与された場合、患者の病状が良好に向かってしまうような、思い込みや期待感から起こる治療効果のこと。 「プラセボ効果」とも呼びます。 |
| 解説(2) |
| 患者のプラシーボ効果 |
昔から「病は気から。。。」というように、 「これは非常によく効く薬だ」 実際に、 |
| 解説(3) |
| 医師のプラシーボ効果 |
また、プラシーボ効果は、医師に対しても起こりうる現象です。 医師に対して、 「絶対に治るはずだ」 |
逆に、もしそれが「プラセボ」ではなく、 面倒くさい臨床試験や治験を実施するぐらいですから、「被験薬」への期待感は当然高いはずです。 「被験薬」を投与された被験者には、 その期待感が、 「被験薬」への「期待効果」は、「プラシーボ効果」と同様に、「真の有効性」以上の「治療効果」を生んでしまう可能性があります。 |
| 解説(4) |
| プラシーボ効果はなくせない |
臨床試験(治験を含む)では、有効性や安全性が科学的に証明されなければなりません。 「プラシーボ効果」「思い込み効果」「期待効果」)は一種の偏り(バイアス)であり、臨床試験の結果の妥当性・信頼性を大きく低下させます。 しかし、「プラシーボ効果」をなくすために、被験者に投与されるのが「プラセボ」か「被験薬」か「実薬」であるかを明らかにしてしまったら、今度は「期待効果」が「被験薬」や「実薬」のほうに、偏って起きてしまいます。 「プラシーボ効果」をなくそうとすることは、比較臨床試験を無意味にしてしまうので、現実的ではありません。 ならば、「被験薬」「実薬」にも「プラシーボ効果」が同じ程度だけ起きるようにする、 それは、被験者に投与されるのが、「プラセボ」「被験薬」「実薬」であるか、完全に分からなくすること。 そのための方法として、 医者と被験者、双方が、 |
なお、被験者を恣意的に特定の治療群(被験薬群、プラセボ群、実薬群など)に割り付けてしまうというバイアス(偏り)が存在します。 そのバイアスをなくすために、ランダム化(無作為化)という作業が必要になります。 |
プラシーボ効果をなくすのではなく、二重盲検とランダム化(無作為化)によって、プラシーボ効果を管理・コントロールする。 それが、 |
| プラセボFAQ インデックス |
| プラセボとは? |
| 1.なぜ、プラセボを使うのか? |
| 2.プラセボは倫理的に問題があるのでは? |
| 3.プラセボについて、インフォームドコンセントはあるか? |
| 4.プラセボが治験に用いられるのは、どんな場合か? |
| 5.プラセボに当たる確率は? |
| 6.プラセボであるかどうかなぜ教えないのか? |
| 7.プラセボに関するヘルシンキ宣言の表記 |
| 関連用語 |
| プラセボ対照試験 |
| ダブルダミー |
| 実薬 |
| 治験薬 |
| 被験薬 |
| 対照薬 |
| 対照 |
| 二重盲検比較試験(DBT) |
| 二重盲検法 (ダブルブラインド法) |
| 盲検化 |
| 単盲検試験 |
| 非盲検試験 |
| 偏り(バイアス) |
| ランダム化(無作為化) |
| ランダム化比較試験(RCT) |
| 上乗せ試験 |
| 薬物有害反応(ADR) |
| 薬物 |
| 医薬品 |
| 医療用医薬品 |
| 薬剤 |
| 戻る/ジャンプ |
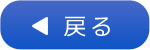 |
| → 用語集インデックス |