| → 用語集インデックス |
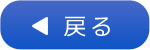 |
| 治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
| 外部対照試験/外部対照 |
| External Control Test / External Control |
| 解説(1) |
| 外部対照試験とは? |
「被験薬を投与される群を含むランダム化比較試験には参加していない患者」(外部対照)で対照群を構成する試験。 従って、「同時にランダム化された対照群が存在しない試験」とも定義できます。 そのため、対照群は、治療される集団と正確に同じ集団から得られるものではありません。 |
通常の2重盲検比較試験では、 外部対照試験では、 |
| 解説(2) |
| 外部対照の時期的分類 |
時期的な分類で言えば、 その試験の実施以前に治療・観察された患者からなる群 の場合と、 同時期であるが他の条件下で治療・観察される群 の場合があります。 |
一般に、既存対照が外部対照として用いられる場合が多いようです。 時には、大規模な外部集団から治療群に類似するように、患者特性に基づいて特定の患者を選んで対照群にすることがあります。 また、特定の対照群と治療群の患者をマッチ(対応)させようとする場合もあります。 |
| なお、外部対照試験は、優越性試験(例えば無治療群との比較)であることも、非劣性試験であることもありえます。 |
| 解説(3) |
| 外部対照試験の長所 |
外部対照試験の主な長所は、全ての患者が有望な薬剤の投与を受けられることです。 この長所があるため、外部対照試験は患者及び医師の双方にとって魅力的なものとなります。 このデザインでは、全ての患者が被験薬を投与されるため、ある意味で効率的だと言え、このことは希少疾病において特に重要です。 |
| 解説(4) |
| 外部対照試験の短所 |
バイアスを制御できないことは、外部対照試験の主たる、そして良く知られた限界です。 多くの場合において、この試験デザインが不適当とされるのは、この限界のためです。 治療群と対照群の比較可能性を確保し、対照群を置く主たる目的を達成することは、外部対照試験では常に困難であり、多くの場合不可能です。 |
試験治療の使用の有無以外に、 ●人口統計学的特性、 試験結果に影響しうる様々な因子が 群間のそのような相違には、重要であるにも関わらず認識さていない予後要因が、観測されることなく、含まれている可能性があります。 外部対照が用いられている場合には、これらのバイアスを最小限にするための盲検化やランダム化を用いることはできません。 その結果、患者、観察者、解析者のバイアスの影響を受けます。 これは重大な短所です。 |
選択バイアスの影響により、無治療既存対照群の結果は、ランダム化比較試験において選ばれる明らかに類似した対照群より、悪い結果となりがちであることは、よく知られています。 ランダム化比較試験における対照群は、試験に入るためのある種の基準、すなわち、一般的に、外部対照群に典型的なものよりも厳しく、より軽症な患者集団を規定することとなる基準を満たさなければなりません。 外部対照群は、しばしばレトロスペクティブに定義され、その結果として選択バイアスが生じる可能性があります。 バイアスを制御できない結果、外部対照試験の知見に説得力を持たせるためには、同時対照試験で必要とされるよりもはるかに厳しい統計学的有意性のレベル、そして非常に大きな治療間の差の推定値が求められることとなります。 外部対照試験では、被験治療の有効性が過大評価される傾向があることもよく知られています。 外部対照試験において実施された統計学的有意性検定は、ランダム化試験において実施されたものに比べ、信頼性が低いことを認識すべきです。 バイアスを制御できないため、外部対照デザインの使用は、治療効果が劇的であり、疾患の通常の経過が十分に予測可能である場合に限定されます。 さらに、外部対照を採用するのは、エンドポイントが客観的であり、エンドポイントに対するベースラインや治療変数の影響の特徴が十分に分かっているような場合に限るべきと言われています。 |
| 関連用語 |
| ベースライン対照試験 |
| 既存対照 |
| 対照 |
| 対照薬 |
| 被験薬 |
| 治験薬 |
| 実薬 |
| 実薬対照試験 |
| プラシーボ効果 |
| ダブルダミー |
| プラセボ対照試験 |
| 二重盲検比較試験(DBT) |
| 盲検化 |
| ランダム化(無作為化) |
| 戻る/ジャンプ |
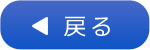 |
| → 用語集インデックス |