| → 用語集インデックス |
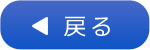 |
| 治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
| 治験施設支援機関(SMO) |
| Site Management Organization |
| 解説(1) |
| 治験施設支援機関(SMO)とは? |
特定の医療機関(治験実施施設)と契約し、その施設に限定して治験業務を支援する機関(通常は企業)。 簡単に言えば、 医薬品開発業務受託機関(CRO)と異なり、医療機関(治験実施施設)側の立場で業務を行うのが特徴です。 「治験施設支援機関」は、長く言いづらいので、通常は「SMO」が使われます。 |
| SMOは、治験に関わる医師、看護婦、事務局の業務を支援することにより、スタッフの負担を軽減し、治験の品質・スピード向上を支援します。 |
| 解説(2) |
| 治験管理業務 |
治験(臨床試験)はGCPという厳しい基準に沿って行われます。 治験の過程で発生する様々な書類 その煩雑かつ膨大な作業を、医師や看護婦が日常の診療の間に行うのは、ほとんど不可能です。 それをサポートするために、SMOが活用されます。 通常は、治験実施施設に設置された「治験事務局」にSMOが作業スタッフを派遣する形態をとります。 なお、業務受託という契約形態をとる場合もあります。 |
| 解説(3) |
| 治験コーディネーター業務 |
GCPという法律によって、 その煩雑な作業を行うために、SMOは、依頼を受けて、看護または薬剤の知識を持った専用のスタッフを治験実施施設に派遣します。 それが、 長いので、通常は略して、「CRC」と呼びます。 なお、業務受託という契約形態をとる場合もあります。 |
| 解説(4) |
| CRO等との独立性について |
2002年11月に厚生労働省から発表された「SMOの利用に関する標準指針策定検討会」報告書で、SMOとCROは「相互に独立性を確保すべき立場である」とされました。 製薬企業もSMOとCROの組織明確化を強く要望しているということもあって、CROを母体とする多くのSMO企業が、経営幹部を親会社と重複させないように交代させました。 また、CROと同一企業である場合は、別会社化あるいは独立組織とするといった措置を行いました。 |
| 解説(5) |
| SMO市場 |
(2005年現在) 日本でもある程度の規模を持つSMOは、10数社存在し、規模の小さいものを含めれば、 さらに多くのSMOがあるようです。 また、一口にSMOと言っても、業務内容によって広範囲にわたるため、医療機関の治験を支援するという広い意味でとらえると、 |
| 解説(6) |
| 業界団体 |
| SMOが加入する団体には、 「日本SMO協会」と 「エスエムオーネットワーク協同組合」 があります。 |
| 日本SMO協会 |
「日本SMO協会」は、 2020年4月現在、業界の主要企業を中心に、約25社のSMOが加盟しています。 結成当時は45社だったので、SMO業界の合併・吸収がいかに進んだかの現れでしょう。 なお、従来の第Ⅰ相試験の受託施設及び受託機関を、中心として構成されていた「臨床試験受託事業協会SMO部会」は、日本SMO協会に合流し、発展的に解消しました。 |
| エスエムオーネットワーク協同組合 |
「エスエムオーネットワーク協同組合」も、治験事務局業務及びCRCの派遣業務を受託する企業(SMO)によって構成されています。 しかし、設立の目的が共同受注にあり、その点において、「日本SMO協会」と趣旨が大きく異なります。 協同組合という法人格を持つことによって、各社が協力して共同受注やCRC教育・育成などに取り組むことで、治験の質向上とスピードアップを図り、製薬企業のニーズに応えていきたいとしています。 |
| 関連用語 |
| 治験コーディネーター (CRC) |
| 治験実施施設 |
| 治験実施医療機関 |
| 海外の治験スピードが速い理由 |
| 治験協力者 |
| 治験事務局 |
| 治験責任医師 |
| 治験分担医師 |
| 治験調整医師 |
| 治験調整委員会 |
| 治験審査委員会(IRB) |
| 医薬品開発業務受託機関 (CRO) |
| 契約書 |
| 戻る/ジャンプ |
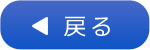 |
| → 用語集インデックス |