| → 用語集インデックス |
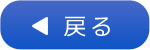 |
| 治験・臨床試験 &医薬品開発用語集 |
| 負担軽減費 (治験協力費) |
| 解説(1) |
| 負担軽減費とは? |
被験者の経済的負担を減らすために、 治験に参加すると、被験者は交通費がかかったり、勤めを休んだりする必要があることから、被験者の金銭的損失を少しでも補うことによって、治験参加率を高めることを目的としています。 「負担軽減費」は、あくまでも、被験者の不利益を救済するための制度であり、謝礼や経済的メリットを目的とはしていません。 そもそも、「治療効果があること」こそが、治験参加の最大のメリットであるはずなのですから。 誰に対する負担軽減であるかを明示するために、「被験者負担軽減費」と呼ぶ場合もあります。 |
| 解説(2) |
| 「負担軽減費」という名称について |
以前は、「治験協力費」とも呼びましたが、 「協力費」という名称だと、治験に「協力」してくれた「謝礼」「報酬」というニュアンスが強く、治験への参加が経済目的(お金目当て)であるかのような印象を与えます。 そこで現在では、 「補助金」の響き(イメージ)がある「負担軽減費」が定着しました。 |
| 解説(3) |
| 負担軽減費は誰が支払うか |
「負担軽減費」は、治験依頼者(製薬企業等)が用意し、治験を実施する医療機関を通して支払われます。 負担軽減費の額は、治験の種類、つまり、 一回の通院につき、大体、7000円前後が目安とされています。 |
| 解説(4) |
| 負担軽減費は必ずしも支払われるとは限らない |
負担軽減費は、治験のために来院することに対して支払われます。 文部科学省の通知で、負担軽減費が、外来患者を想定して記述されていたためです。 従って、もともと入院している方の場合、来院という作業が発生しないので、本来は負担軽減費は支払う必要はありません。 また、治験のためのみに入院する必要がある場合は、入院と退院を1セットとして、1回分支払われます。 なぜなら、支払われないからです。 しかし、負担軽減費には、「治験に参加することによる被験者の精神的負担を、経済的な面から補填する」という意味があることも確かです。 そのため、入院している被験者にも、ある程度の額の「負担軽減費」を支払うべきだ また、病院のすぐ近くに住んでいるため、 「それでは、入院している被験者と大して変わらないではないか?」 という矛盾もはらんでいます。 |
| 解説(5) |
| 負担軽減費支給制限の例外 |
なお、上記のような制限があるのは、国立の医療機関の場合です。 私立の医療機関の場合は、各医療機関の事情に応じて多少の裁量が認められています。 治験審査委員会で事前に協議して決めた「過剰でない範囲の金額」で、負担軽減費を支払うことが可能です。 入院患者、製造販売後臨床試験の参加者、医療機関近所からの通院患者などに対して、負担軽減費支給の自由度を認めることは、治験の推進には不可欠であると考えられます。 |
| 関連Q&A |
| 治験Q&A:治験に参加したらお金(謝礼)をもらえるのか? |
| 治験Q&A:治験を受けるメリットは? |
| 関連用語 |
| 被験者 |
| 被験者の福祉 |
| 製造販売後臨床試験 |
| 白ラベル(白箱) |
| 戻る/ジャンプ |
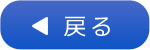 |
| → 用語集インデックス |